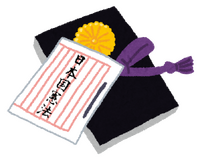地震予知
今日の朝刊や昨日のネットニュースなどで「南海トラフ地震の直前予知は、100回行っても99回は失敗する」という記事が報じられました。
現在では中学の教科書にも『プレートテクトニクス』という理論が載っています。
しかし、1980年代の高校地学の教科書では、造山運動のメカニズムとして『地向斜造山論』と『プレートテクトニクス』が同等に併記されており、それ以前は『地向斜造山論』が主流で『プレートテクトニクス』は「新しい理論」として紹介されていました。
つまり、地震メカニズムの根幹をなす『プレートテクトニクス』の考え方でさえ、定着したのはここ40年ぐらいのことなのです(そう考えると小松左京の『日本沈没』が1973年に出版されていることはスゴイことですよね)。
このプレートは地球表面の「地殻」と「マントル上部」をあわせたおよそ100kmのかたい部分(リソスフェア)と言われていますが、人類は実際には12kmくらいまでしか掘ったことはありません。
実は、私たちが暮らす地球について、わかっていることのほうが少ないのです。
「遺伝子工学」や「AI」など最先端の分野に目が行きがちですが、子どもたちの中から「地球の謎」に迫る研究者が育ってくれれば、将来的に地震予知の確率も上がってくるのかもしれません。
きょうは少しかたい話になってしまました(プレートだけに・・・)。
オヤジギャグはやめようと思った学長でした。