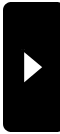G・W 始まりました!
一応(?) G・Wに突入しました。
ということで、早速1コマ
 講座?
講座?
いやいや違います。
マンツーマンですよ。
生徒ひとりのための板書です。
反応を見ながら、じっくりと解説させていただきました。
会話の中でかなり理解できているとは思いましたが、
まだまだ安心はできません。
次回、もう一度チェックしますからネ。
以上、学長でした。
ということで、早速1コマ
 講座?
講座?いやいや違います。
マンツーマンですよ。
生徒ひとりのための板書です。
反応を見ながら、じっくりと解説させていただきました。
会話の中でかなり理解できているとは思いましたが、
まだまだ安心はできません。
次回、もう一度チェックしますからネ。
以上、学長でした。
漢字テストを繰り返し
校長の鈴木です。
最近、「漢字(とくに書き)」が苦手だという中学生のお子さんがよくいらっしゃいます。
みんな白文帳で練習しているのですが、だんだん提出することが目的になって
「手の運動」と化していることが少なくありません。
そこで・・・
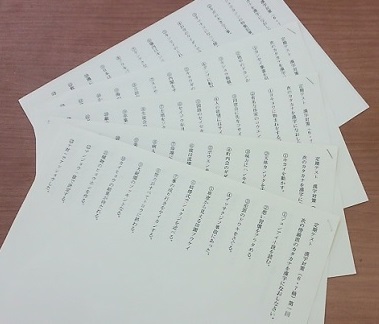 例によって漢字テストを作り、国語の授業では毎回生徒に
例によって漢字テストを作り、国語の授業では毎回生徒に
テストしています。
見ないでちゃんと書けるかをやっぱりテストしなきゃですね。
「7級」から「3級」まで一人ひとりに個別につくっていたら
気がつけばワードファイル80ページ分にも・・・
とっても当たり前なことを1つ。漢字を書いて練習するときは「丁寧に」「正確に」。
漢字を「画像」として覚える傾向の人もわりといるようで、歪んで書いていたり雑になって書いていると
そのまま、歪んだ形で覚えてしまいます。そうすると思いだす時にうまく思いだせません。
間違えた漢字をやり直す時は「大きく」書いた方がよいですね。
ちょこちょこっと小さな字で書いてもなんだか頭に残りません。
「思いだして書く」、この繰り返しに、とことん伴走していきます。
最近、「漢字(とくに書き)」が苦手だという中学生のお子さんがよくいらっしゃいます。
みんな白文帳で練習しているのですが、だんだん提出することが目的になって
「手の運動」と化していることが少なくありません。
そこで・・・
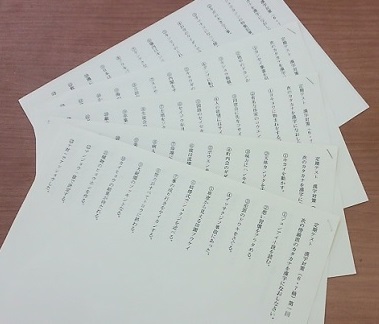 例によって漢字テストを作り、国語の授業では毎回生徒に
例によって漢字テストを作り、国語の授業では毎回生徒にテストしています。
見ないでちゃんと書けるかをやっぱりテストしなきゃですね。
「7級」から「3級」まで一人ひとりに個別につくっていたら
気がつけばワードファイル80ページ分にも・・・
とっても当たり前なことを1つ。漢字を書いて練習するときは「丁寧に」「正確に」。
漢字を「画像」として覚える傾向の人もわりといるようで、歪んで書いていたり雑になって書いていると
そのまま、歪んだ形で覚えてしまいます。そうすると思いだす時にうまく思いだせません。
間違えた漢字をやり直す時は「大きく」書いた方がよいですね。
ちょこちょこっと小さな字で書いてもなんだか頭に残りません。
「思いだして書く」、この繰り返しに、とことん伴走していきます。
子供たちの暮らす未来
今日は少し硬い話になります。
国内総生産(GDP)とは、その国の中で「新たに生み出されたモノやサービス」の量を金額で表したものです。
このGDPの伸び率を経済成長率と言います。
日本の場合、1955年~1975年の約20年間を見てみますと(当時は国民総生産GNPでしたが)、
1955年の9兆円から、1975年の152兆円へと驚異的な伸びを示しています(いずれも名目GDPです)。
これに対して、1994年~2014年の約20年間を見てみますと、
1994年には496兆円だったものが、2014年には488兆円となっています。
この間、500兆円を上回る年もあり若干の増減はありましたが、ほぼ横ばい状態にあります。
生活の豊かさは何も経済的なものばかりではなく、精神的なもの、さらには環境への配慮なども考えるべきであることは言うまでもありません。
しかし、国民全員が、「昨日より今日」「今日より明日」と少なくとも『経済的』に豊かになっていくためには、その大元(おおもと)となる「パイ」=「消費」を大きくしていくことが必要であると考えている人たちがいることも事実です。
一方、日本の人口は減少傾向にあり、人口構造も極端な少子高齢化となっています。すなわち、このままでは国内の消費も減少していくことはほぼ明らかであり、人口の減少によってGDPを支えている労働人口もまた減少していきます。
このような経済環境の中、今の子供たちが社会の中心を担う頃、日本社会はどのようになっているのでしょうか?
ひとつには、国内の「パイ(消費)」の増加が見込めない以上、これまで以上に海外需要を求めることになるでしょう。平たく言えば、商売の相手がさらに国外になるということです。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)も、その是非は別として、この考えの一環であるといえます。
さらに、労働人口の減少に伴い、海外から優秀な労働力が流入してくるでしょう。加えて、現行法では原則禁じられていますが単純労働者の就労も認められるようになってくるかもしれません。
その中で、日本人労働者には、高度な知的労働、対外的な折衝能力、外国人労働者を取りまとめる能力、様々な能力が求められることになるのでしょうか。
もしかしたら単なる気苦労、考えすぎかもしれません。しかし、今とは大きく異なる社会が近づいてきてる、そう考え、備えておくことが無難だと思います。
「語学力」は大学に入ってからでも、社会人になってからでも身につきますが、子供たちにはまず、「自分の頭で粘り強く考え抜く力」、「高度な専門能力を習得するための基礎学力」をしっかりと身につけてもらいたいと考えています。
私も子を持つひとりの親として、「職場の上司がある日突然外国人になっていた」、これがCMの中だけの笑い話で終わってもらえればと、心のどこかで思っている自分がいます。
以上、学長でした。
国内総生産(GDP)とは、その国の中で「新たに生み出されたモノやサービス」の量を金額で表したものです。
このGDPの伸び率を経済成長率と言います。
日本の場合、1955年~1975年の約20年間を見てみますと(当時は国民総生産GNPでしたが)、
1955年の9兆円から、1975年の152兆円へと驚異的な伸びを示しています(いずれも名目GDPです)。
これに対して、1994年~2014年の約20年間を見てみますと、
1994年には496兆円だったものが、2014年には488兆円となっています。
この間、500兆円を上回る年もあり若干の増減はありましたが、ほぼ横ばい状態にあります。
生活の豊かさは何も経済的なものばかりではなく、精神的なもの、さらには環境への配慮なども考えるべきであることは言うまでもありません。
しかし、国民全員が、「昨日より今日」「今日より明日」と少なくとも『経済的』に豊かになっていくためには、その大元(おおもと)となる「パイ」=「消費」を大きくしていくことが必要であると考えている人たちがいることも事実です。
一方、日本の人口は減少傾向にあり、人口構造も極端な少子高齢化となっています。すなわち、このままでは国内の消費も減少していくことはほぼ明らかであり、人口の減少によってGDPを支えている労働人口もまた減少していきます。
このような経済環境の中、今の子供たちが社会の中心を担う頃、日本社会はどのようになっているのでしょうか?
ひとつには、国内の「パイ(消費)」の増加が見込めない以上、これまで以上に海外需要を求めることになるでしょう。平たく言えば、商売の相手がさらに国外になるということです。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)も、その是非は別として、この考えの一環であるといえます。
さらに、労働人口の減少に伴い、海外から優秀な労働力が流入してくるでしょう。加えて、現行法では原則禁じられていますが単純労働者の就労も認められるようになってくるかもしれません。
その中で、日本人労働者には、高度な知的労働、対外的な折衝能力、外国人労働者を取りまとめる能力、様々な能力が求められることになるのでしょうか。
もしかしたら単なる気苦労、考えすぎかもしれません。しかし、今とは大きく異なる社会が近づいてきてる、そう考え、備えておくことが無難だと思います。
「語学力」は大学に入ってからでも、社会人になってからでも身につきますが、子供たちにはまず、「自分の頭で粘り強く考え抜く力」、「高度な専門能力を習得するための基礎学力」をしっかりと身につけてもらいたいと考えています。
私も子を持つひとりの親として、「職場の上司がある日突然外国人になっていた」、これがCMの中だけの笑い話で終わってもらえればと、心のどこかで思っている自分がいます。
以上、学長でした。
こんなに違うの?
私事で恐縮ですが、
私には、4本中3本の親不知(おやしらず)が残っていました。
唯一左下の親知らずを抜いたのは、今から30年以上前の1月。
忘れもしない『共通一次』(古い )の1週間ほど前でした。
)の1週間ほど前でした。
抜くのにひと苦労で、抜いたあとも3日ほど出血が止まらず・・・
とにかく大変な思いをしたのをよーく覚えています。
それ以来、親不知を抜くことがトラウマとなり3本もの親不知を
大事に抱え込むはめになったのです。
ところが、昨日その親不知たちが謀反を起こし(笑)、
やむを得ず歯医者さんに駆け込むはめになりました。
診察の結果、右下の親不知がひどいので、急遽抜歯することになりました。
「親不知トラウマ」を抱える私としては、一瞬「えっ」と思いましたが、
あまりの痛さに、「お願いします」とすがるしかありませんでした。
ところが、予想に反して、楽に終わったのです。
生え方が悪いのは自分でもわかっていました。
先生も「これは結構大変ですよ」と言ってくださいました。
でも30年前のあの『惨劇?』に比べると雲泥の差です。
「えっ、これで終わり?」 と思うほどあっさりと終わってしまったのです。
先生の腕の良さも当然あるのでしょうが、
30年のうちに様々な技術も進歩してきたのでしょう。
そしてその技術の進歩の礎となるのが「教育」なのだと
改めて考えさせられました。
技術の進歩のおかげで、
抜歯した日も、3コマ授業に入ったことは言うまでもありません。
以上 学長でした。
私には、4本中3本の親不知(おやしらず)が残っていました。
唯一左下の親知らずを抜いたのは、今から30年以上前の1月。
忘れもしない『共通一次』(古い
 )の1週間ほど前でした。
)の1週間ほど前でした。抜くのにひと苦労で、抜いたあとも3日ほど出血が止まらず・・・
とにかく大変な思いをしたのをよーく覚えています。
それ以来、親不知を抜くことがトラウマとなり3本もの親不知を
大事に抱え込むはめになったのです。
ところが、昨日その親不知たちが謀反を起こし(笑)、
やむを得ず歯医者さんに駆け込むはめになりました。
診察の結果、右下の親不知がひどいので、急遽抜歯することになりました。
「親不知トラウマ」を抱える私としては、一瞬「えっ」と思いましたが、
あまりの痛さに、「お願いします」とすがるしかありませんでした。
ところが、予想に反して、楽に終わったのです。
生え方が悪いのは自分でもわかっていました。
先生も「これは結構大変ですよ」と言ってくださいました。
でも30年前のあの『惨劇?』に比べると雲泥の差です。
「えっ、これで終わり?」 と思うほどあっさりと終わってしまったのです。
先生の腕の良さも当然あるのでしょうが、
30年のうちに様々な技術も進歩してきたのでしょう。
そしてその技術の進歩の礎となるのが「教育」なのだと
改めて考えさせられました。
技術の進歩のおかげで、
抜歯した日も、3コマ授業に入ったことは言うまでもありません。
以上 学長でした。
△△を制する者は・・・
ボクシングの世界で、
『左を制する者は世界を制す』という言葉があります。
ジャブの重要性を説いたものだそうです。
ずいぶん前に、「あしたのジョー」か「リングにかけろ」か
(どちらにしても古いですよネ)で見たような気がします。
ところで、自習室には「メモ用の裏紙」が置いてあります。

その「メモ用の裏紙」の前に書いてあるのが、

自習室とメモ用紙を最大限に活用して、
『受験』を制してください。
学長
『左を制する者は世界を制す』という言葉があります。
ジャブの重要性を説いたものだそうです。
ずいぶん前に、「あしたのジョー」か「リングにかけろ」か
(どちらにしても古いですよネ)で見たような気がします。
ところで、自習室には「メモ用の裏紙」が置いてあります。

その「メモ用の裏紙」の前に書いてあるのが、

自習室とメモ用紙を最大限に活用して、
『受験』を制してください。
学長
待ってくれている人
私も毎日夜10時まで授業に入っています。
ですから、質問を受けられるのはどうしてもそれ以降になってしまいます。
申し訳ない思いでいっぱいですが、それでも待ってくれている生徒がいます。
昨日も、激しい雨にもかかわらず質問を待ってくれている生徒がいました。
幸い家も近く、ご家庭への連絡を確認した上で質問の対応を行ないました。
まだ高校1年生ですが、学校の進度が速く、すべての問題の説明に1時間
ほどかかり、終わったのは11時でした。
これが秋ごろになると、質問の順番待ちとなり、最後の質問が終わるのが
12時近くになることも珍しくありません。
大変だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは逆です。
頼りにして待っていてくれる生徒がいるといういうのは講師冥利につき、
疲れも一気にふっとんでしまいます。
生徒の本気に、本気で応えることができる。
この仕事の楽しいところです。
学長
ですから、質問を受けられるのはどうしてもそれ以降になってしまいます。
申し訳ない思いでいっぱいですが、それでも待ってくれている生徒がいます。
昨日も、激しい雨にもかかわらず質問を待ってくれている生徒がいました。
幸い家も近く、ご家庭への連絡を確認した上で質問の対応を行ないました。
まだ高校1年生ですが、学校の進度が速く、すべての問題の説明に1時間
ほどかかり、終わったのは11時でした。
これが秋ごろになると、質問の順番待ちとなり、最後の質問が終わるのが
12時近くになることも珍しくありません。
大変だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは逆です。
頼りにして待っていてくれる生徒がいるといういうのは講師冥利につき、
疲れも一気にふっとんでしまいます。
生徒の本気に、本気で応えることができる。
この仕事の楽しいところです。
学長
『塾』の「やる気」
昔、明石家さんまがジミー大西に
「頑張れよ」と言うと
「お前もな」と返されるギャグがありあした。
(かなり古いので、今の生徒は知らないでしょうネ)
実は、私たちも生徒に
「頑張れよ」と言ったときに
「お前もな」と返されないように気をつけています(笑)。
どういうことかと言うと、
いつも 「休みの日には△△時間は勉強しろよ」 と言っておきながら、
休みの日に「塾はお休みです」「自習室は使えません」では、
『お前もな』と厳しいツッコミを受けてしまうからです。
生徒にやる気を求める前に、『塾』のやる気を見せる。
当然のことですが「クレアカ」は
普段から土日祝日も開けていますし、
ゴールデンウィークもフル・オープン
自習室も、土日祝日は10:00~22:00 で利用できます。
これが『塾』の「やる気」です。
次は皆さんの「やる気」を期待しています。
辛島
「頑張れよ」と言うと
「お前もな」と返されるギャグがありあした。
(かなり古いので、今の生徒は知らないでしょうネ)
実は、私たちも生徒に
「頑張れよ」と言ったときに
「お前もな」と返されないように気をつけています(笑)。
どういうことかと言うと、
いつも 「休みの日には△△時間は勉強しろよ」 と言っておきながら、
休みの日に「塾はお休みです」「自習室は使えません」では、
『お前もな』と厳しいツッコミを受けてしまうからです。
生徒にやる気を求める前に、『塾』のやる気を見せる。
当然のことですが「クレアカ」は
普段から土日祝日も開けていますし、
ゴールデンウィークもフル・オープン
自習室も、土日祝日は10:00~22:00 で利用できます。
これが『塾』の「やる気」です。
次は皆さんの「やる気」を期待しています。
辛島
G・W 特訓講座!
今年もやります!
中学3年生対象
高校受験対策 『G・W 特訓講座』 開講!!
期間:4/29~5/6
「部活が終わってから?」「夏休み頃から?」
受験体制に入るのに、早すぎるということはありません。
むしろ、人がやっていない時期だからこそ
差をつけることができるのです。
まさに『先手必勝』です。
※詳細につきましては教室にお問い合わせください。
当然 クレアカはG・Wもフルオープン
土日祝日は自習室も
朝10時から夜10時まで 利用できます。
高校生は「特講」はありませんが、
自習室をフル活用してください。
中学3年生対象
高校受験対策 『G・W 特訓講座』 開講!!
期間:4/29~5/6
「部活が終わってから?」「夏休み頃から?」
受験体制に入るのに、早すぎるということはありません。
むしろ、人がやっていない時期だからこそ
差をつけることができるのです。
まさに『先手必勝』です。
※詳細につきましては教室にお問い合わせください。
当然 クレアカはG・Wもフルオープン
土日祝日は自習室も
朝10時から夜10時まで 利用できます。
高校生は「特講」はありませんが、
自習室をフル活用してください。
『やればできる』はホント? 完結編
さて、はじめ思っていたより長くなってしまいましたが、いよいよ「完結編」となります。
とは言っても、前回の「妨げている要因」が単純なものであっただけに、それらを「取り除く方法」もきわめて単純です。
1.『「わからない」だから「やらない」』を取り除くには
当然「わかる」ようにしてあげればいいだけです。
ただ、この「わかるようにする」ことにも誤解があるのです。
ある問題が解けない子どもがいたとします。その問題を説明してあげると、本人は「わかった!」と嬉しそうにしてくれます。しかし、問題は何も解決していません。その問題が解けなかった原因にまでさかのぼって理解してもらわなければ、本当に自力で解けるようにはならないのです。
そして、ここが意外と大きなポイントなのですが、『本人が「理解できている」と言っている(そう思っている)』ところに、実は解けない原因が隠れていることが少なくありません。
当然本人には理解できていないという自覚症状はないのですから、こちら側で「本当に理解できているのか」「理解できていると思い込んでいるだけなのか」のチェックを行う必要があります。これには結構手間がかかります。ときには解いている過程をじっと観察する必要さえあるのです。
しかし、このようにして原因を取り除いていけば、徐々にですが自分で進めることができるようになっていきます。
2. 『頭と体がついてこない』を取り除くには
ひと言で言うと、『鍛える』しかありません。かなり乱暴な言い方に聞こえるかもしれませんが、前提として、子供は『学習体力』さえ身につければかなりの時間「自主的に」勉強を続けることができるようになる、という確信があります。
中学3年生など、春先には2時間程度の学習でも根を上げていた子供たちも、夏期講習を経て秋ごろになると休日には平気で6~8時間ほど学習できるようになってきます。
『学習体力』をつけるポイントは主にふたつです。
ひとつは周囲が限界点を低く設定しないことです。「量よりも質が大事」「集中力は長くは続かない」確かにそうかもしれません。しかし周囲がそう言ってしまうと、子供もそれでいいのかと考えてしまいます。周囲が求めるべきは『質×量』の最大化です。
もうひとつは、伴走してあげることです。今までできなかったことをできるようにする、大げさかもしれませんが、今まで勉強してこなかった子供たちにとっては『未知の世界』に踏み出すことなのです。長時間勉強をしている自分など想像すらできないでしょう。最初は道を知っている誰かが付き添って走ってあげることが必要です。
正しい方法で鍛えてあげさえすれば、『学習体力』が身につき「自主的に」勉強に取り組むことも可能になります。
ここまで本当に長々とお付き合いただき、ありがとうございます。
『やらなければできない』。ではどうすれば「やるようになる」のか?
結局は、「子供を信じて適切な方法で支えてあげる」、これに尽きます。
世の中には『自立学習』という便利な言葉があります。これは我々が目指すべき大切な目標のひとつであることに間違いありません。しかし、時としてこの言葉が「本人任せの放任指導」を正当化するのに使われることも少なくありません。本当に自立させるためには手をかけることが求められる、私はそう信じています。
わたくし共にもまだまだ足りない点が多々あるかとは思いますが、生徒一人ひとりをしっかりと見守っていけるよう、これからも全力を尽くして参ります。
辛島
とは言っても、前回の「妨げている要因」が単純なものであっただけに、それらを「取り除く方法」もきわめて単純です。
1.『「わからない」だから「やらない」』を取り除くには
当然「わかる」ようにしてあげればいいだけです。
ただ、この「わかるようにする」ことにも誤解があるのです。
ある問題が解けない子どもがいたとします。その問題を説明してあげると、本人は「わかった!」と嬉しそうにしてくれます。しかし、問題は何も解決していません。その問題が解けなかった原因にまでさかのぼって理解してもらわなければ、本当に自力で解けるようにはならないのです。
そして、ここが意外と大きなポイントなのですが、『本人が「理解できている」と言っている(そう思っている)』ところに、実は解けない原因が隠れていることが少なくありません。
当然本人には理解できていないという自覚症状はないのですから、こちら側で「本当に理解できているのか」「理解できていると思い込んでいるだけなのか」のチェックを行う必要があります。これには結構手間がかかります。ときには解いている過程をじっと観察する必要さえあるのです。
しかし、このようにして原因を取り除いていけば、徐々にですが自分で進めることができるようになっていきます。
2. 『頭と体がついてこない』を取り除くには
ひと言で言うと、『鍛える』しかありません。かなり乱暴な言い方に聞こえるかもしれませんが、前提として、子供は『学習体力』さえ身につければかなりの時間「自主的に」勉強を続けることができるようになる、という確信があります。
中学3年生など、春先には2時間程度の学習でも根を上げていた子供たちも、夏期講習を経て秋ごろになると休日には平気で6~8時間ほど学習できるようになってきます。
『学習体力』をつけるポイントは主にふたつです。
ひとつは周囲が限界点を低く設定しないことです。「量よりも質が大事」「集中力は長くは続かない」確かにそうかもしれません。しかし周囲がそう言ってしまうと、子供もそれでいいのかと考えてしまいます。周囲が求めるべきは『質×量』の最大化です。
もうひとつは、伴走してあげることです。今までできなかったことをできるようにする、大げさかもしれませんが、今まで勉強してこなかった子供たちにとっては『未知の世界』に踏み出すことなのです。長時間勉強をしている自分など想像すらできないでしょう。最初は道を知っている誰かが付き添って走ってあげることが必要です。
正しい方法で鍛えてあげさえすれば、『学習体力』が身につき「自主的に」勉強に取り組むことも可能になります。
ここまで本当に長々とお付き合いただき、ありがとうございます。
『やらなければできない』。ではどうすれば「やるようになる」のか?
結局は、「子供を信じて適切な方法で支えてあげる」、これに尽きます。
世の中には『自立学習』という便利な言葉があります。これは我々が目指すべき大切な目標のひとつであることに間違いありません。しかし、時としてこの言葉が「本人任せの放任指導」を正当化するのに使われることも少なくありません。本当に自立させるためには手をかけることが求められる、私はそう信じています。
わたくし共にもまだまだ足りない点が多々あるかとは思いますが、生徒一人ひとりをしっかりと見守っていけるよう、これからも全力を尽くして参ります。
辛島
『やればできる』はホント? の続き
前回、肝心なところで終わってしまい申し訳ありませんでした。
嬉しいことですが、催促も頂戴いたしましたので早速続きをアップします。
「勉強しなければならない」とわかっているのに机に向かわせない原因、勉強するのを妨げている主な要因は二つあります。「要因」などと言うと難しそうな感じもしますが、ものすごく単純な話です。「な~んだ、そんなことか。」と思われるかもしれませんが(いや思われると思いますが)最後まで聞いてください。
妨げている要因その① 【「わからない」だから「やれない」】
ふだん勉強しない子供でも、テスト前やテストの結果が悪かったとき、たまには「勉強しようかな」と机に向かってみることはあると思います。
教科書・問題集を広げ、問題を解いてみる。「解けない」「手も足も出ない」、どうしようもなく数分後にはあきらめて机の前を離れ横になっている。
程度の差こそあれ、想像に難くないシーンです。この傾向は、特に積み上げ式の教科である「数学」「英語」によくみられます。中には、机から離れることはなくとも、他の教科「社会」などに避難するパターンなどもみられます。
せっかく「やってみよう」という気になっても、理解できないのであればやりようがありません。「わからない」だから「やれない」、当然のことではありますが、「やる気」の問題ではなく子供自身も苦しんでいるということを理解してあげてください。
妨げている要因その② 【体と頭がついてこない】
ほとんど運動をしていない人に、いきなり「毎日10km走りなさい」と言っても無理な話です。一日ぐらいは奇跡的にできたとしても二日とは続けられないでしょう。
運動で例えるとすぐに理解してもらえますが、こと勉強については意外と理解されていません。「その気にさえなれば1~2時間は勉強できる」と、ほとんどの人が思っています。
しかし慣れていないと、机の前に自主的に1時間「座り続ける」ことさえ苦痛なのです。ましてや1時間「勉強し続ける」となると、体だけではなく頭もバテてしまいます。(ちなみに学校などで「受身で勉強する」のと、自ら進んで「自主的に」勉強するのは根本的に違います。このことは、また別のコラムでお話したいと思います。)
勉強するためにも、勉強に向けた体と頭の持久力が必要なのです。私はこれを『学習体力』と言っていますが、『学習体力』の備わっていない段階で、いきなり自主的に長時間学習することを求めるのは、先の「10km走る」場合と同様に当然無理なことなのです。
では、どうすればよいのか? どうすればこれら2つの「妨げている要因」を取り除くことができるのか?
申し訳ありません。またまた長くなってしまいましたので、次回「完結編」とさせていただきます。 辛島
嬉しいことですが、催促も頂戴いたしましたので早速続きをアップします。
「勉強しなければならない」とわかっているのに机に向かわせない原因、勉強するのを妨げている主な要因は二つあります。「要因」などと言うと難しそうな感じもしますが、ものすごく単純な話です。「な~んだ、そんなことか。」と思われるかもしれませんが(いや思われると思いますが)最後まで聞いてください。
妨げている要因その① 【「わからない」だから「やれない」】
ふだん勉強しない子供でも、テスト前やテストの結果が悪かったとき、たまには「勉強しようかな」と机に向かってみることはあると思います。
教科書・問題集を広げ、問題を解いてみる。「解けない」「手も足も出ない」、どうしようもなく数分後にはあきらめて机の前を離れ横になっている。
程度の差こそあれ、想像に難くないシーンです。この傾向は、特に積み上げ式の教科である「数学」「英語」によくみられます。中には、机から離れることはなくとも、他の教科「社会」などに避難するパターンなどもみられます。
せっかく「やってみよう」という気になっても、理解できないのであればやりようがありません。「わからない」だから「やれない」、当然のことではありますが、「やる気」の問題ではなく子供自身も苦しんでいるということを理解してあげてください。
妨げている要因その② 【体と頭がついてこない】
ほとんど運動をしていない人に、いきなり「毎日10km走りなさい」と言っても無理な話です。一日ぐらいは奇跡的にできたとしても二日とは続けられないでしょう。
運動で例えるとすぐに理解してもらえますが、こと勉強については意外と理解されていません。「その気にさえなれば1~2時間は勉強できる」と、ほとんどの人が思っています。
しかし慣れていないと、机の前に自主的に1時間「座り続ける」ことさえ苦痛なのです。ましてや1時間「勉強し続ける」となると、体だけではなく頭もバテてしまいます。(ちなみに学校などで「受身で勉強する」のと、自ら進んで「自主的に」勉強するのは根本的に違います。このことは、また別のコラムでお話したいと思います。)
勉強するためにも、勉強に向けた体と頭の持久力が必要なのです。私はこれを『学習体力』と言っていますが、『学習体力』の備わっていない段階で、いきなり自主的に長時間学習することを求めるのは、先の「10km走る」場合と同様に当然無理なことなのです。
では、どうすればよいのか? どうすればこれら2つの「妨げている要因」を取り除くことができるのか?
申し訳ありません。またまた長くなってしまいましたので、次回「完結編」とさせていただきます。 辛島