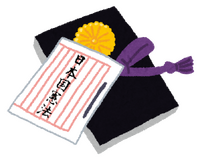分水嶺
昨日の話の続きです。
2021年からの入試制度の改革で、英語は民間試験を導入し、「読む」「聞く」「話す」「書く」といった「4技能評価への転換」を目指している、という話の続きです。
この転換の背景には、「高度に英語を使いこなせる人材」を求める経済界の意向も働いているのでしょう。経済界としては当然の要望です。
ただ、「日本の英語教育は、中・高・大と10年間も学習しているのに話すこともできない。」
このような議論は今に始まったことではありません。
今から30年ほど前にも「『読む』『書く』はできるが、「話す」ができない」という指摘の下、カリキュラムが変更され、「オーラルコミュニケーション」などが高校英語に導入されました。
そして、その結果「学生が『読めない』『書けない』『話せない』状態になってしまった」という指摘を大学側から受ける結果となったのです。
その後「ゆとり教育」と相まって、学生の英語力は著しく低下していきました。
そもそも国公立大学は、これまでも「二次試験」「個別試験」を通じて「読む」「書く」能力を受験生に求めてきました。
受験科目を含めた募集要項は、大学側が自分のところで学んで欲しい学生を選抜するための主体的な戦略そのものです。
そこに各大学が「民間試験」をどのように組み込んでいくのか。

「大学の方が時代遅れなんだ」 たしかにそういったご意見もあるでしょう。
しかし、日本に「学問の自由」は根付いているのか、「大学の自治」はアンシャン・レジームと化してしまうのか、またひとつ分岐点が訪れているような気がするのは、単に私の考えすぎなのでしょうか。
以上、学長でした。