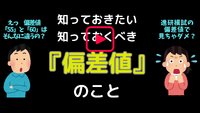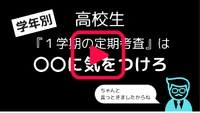センター試験 数学ⅡB編
昨日に引き続き センター試験を解いてみての感想
今日は 数学ⅡBの感想です
ⅡBの問題は ありがたいことに 毎年解くごとに 体力の衰えを実感させてくれます
相変わらず それだけの計算量を要求しているということです
『解き方』はわかっても正答にたどり着くまでの『処理』ができるかどうかがポイントで
むしろ後者の方にウエイトがあるようにも感じられます
ただ計算量にしても よく考えられているのか どの大問も(第5問は除く)1問につき 丁寧目に計算してB5の用紙1枚弱に計算が納まりました

今日は 数学ⅡBの感想です
ⅠAのような問題点はみられず例年通りのようでしたが 設問間の『段差』にバラつきが有り 少し作りが丁寧さに欠けているように感じたのは私の思いすごしですかね
数列で一度ミスをしたので ギリギリ60分でぐったりしました
むしろ後者の方にウエイトがあるようにも感じられます
内容的には
第1問(三角関数 指数関数・対数関数)
基本的な変形問題ですが「自分が今何をしようとしているのか」ということを意識しておくことが大切だったと思います
第2問(微分法・積分法)
ここも頻出の「共通接線」と「面積」の問題でしたが 後半のかなりの量の設問が「1/3の公式」を必須アイテムのようにしていた(さすがにこれを使わずに時間内は厳しいのでは)のはいかがなものかとは思いました
第3問(数列)
「数列的な要素がどこにあるの?」というのが率直な感想です (4)などは「急に何を言い出すの」と思った人も多かったと思います
第4問(ベクトル)
(3)の前半までは比較的スムーズにいけたかと思います 分かれ目は(3)の「図形の選択」だったでしょう (4)は具体的に図形をイメージできなくても∠CODの大きさを求めさせられたことから 「これかな?」で押し切れた人もいたかもしれません
ついでに時間外で解いた
第5問(確率分布と統計的な推測)
例年通り楽ですね この分野は「確率」と「統計」を半ば強引に結びつけたものなので これ以上の問題は作れないのでしょう ただこの分野を授業で正式に扱う高校はほとんどありませんが・・・
ちなみに「大学入試共通テスト」の施行調査問題では この「確率分布と統計的な推測」が第3問に『格上げ?』されていますよね
そのあたりも含めて 明日は「共通テスト」の話をする予定です
昨日に続きざっくりとした感想だけで申し訳ありません
このあと 14:40から二次試験対策の指導です
祈 合格!!

以上 学長でした