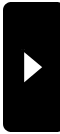あなたなら何と答えますか?
唐突ですみません。
私と一番上のいとことは20歳年が離れています。ですから、そのいとこの長女は私の4才年下です。
彼女は屋代高校を卒業し、そのままアメリカの大学に留学しました(当時の言葉では「翔んでた(完全な死語)」んですね)。
大学を卒業したあともそのまま現地で就職し、今もニューヨークで暮らしています。
7・8年ほど前に、彼女がアメリカ人の旦那さんといっしょに帰国し、その際私のところにも泊りがけで遊びに来てくれました。
その旦那さんから受けたのが「なぜ日本の総理大臣はあんなにコロコロ代わるんだ」という質問でした。
当時平成18年の安倍第一次内閣から平成24年の野田内閣まで6年間で6人の総理大臣が交代していました。
あなたなら何と答えますか?
私も一瞬どう答えれば良いか迷いました。
「アメリカは大統領制で一旦当選すると弾劾されない限り4年の任期保証されている」

ほかにもいろんな答えはあるでしょうが、私の出した答えは、「先進国の中で、議院内閣制を採用していてかつ議会の二院制が正当に機能しているのは日本ぐらいのものだからだよ」というものでした。
議院内閣制の内容もわからない相手に、英語で説明するのは大変でした。分からない単語は電子辞書で調べながらなんとか理解してもらいました(本当に理解してもらえたのかな?)
議院内閣制では、行政権の長は直接国民からは選ばれず、議会の信任を必要とします。またイギリスも議院内閣制をとっていますが、議会の上院は非民選で下院が圧倒的に優越しているため『ねじれ現象』など起こらないのですね。
島崎先生がきのうのブログで、外国語で「話す中身・伝える中身」を身につけることが大切だと書かれていたのを読んで思い出したエピソードでした。
ちなみ後できいたところによると、その旦那さん、会う日本人みんなに同じ質問をしては反応を見て半ば楽しんでいたようです。気のいい人なんですけどね。とりあえず矜持は保てたというところでしょうか。
以上、学長でした。
私と一番上のいとことは20歳年が離れています。ですから、そのいとこの長女は私の4才年下です。
彼女は屋代高校を卒業し、そのままアメリカの大学に留学しました(当時の言葉では「翔んでた(完全な死語)」んですね)。
大学を卒業したあともそのまま現地で就職し、今もニューヨークで暮らしています。
7・8年ほど前に、彼女がアメリカ人の旦那さんといっしょに帰国し、その際私のところにも泊りがけで遊びに来てくれました。
その旦那さんから受けたのが「なぜ日本の総理大臣はあんなにコロコロ代わるんだ」という質問でした。
当時平成18年の安倍第一次内閣から平成24年の野田内閣まで6年間で6人の総理大臣が交代していました。
あなたなら何と答えますか?
「アメリカは大統領制で一旦当選すると弾劾されない限り4年の任期保証されている」
「日本の総理大臣がコロコロ代わっているのは『ねじれ国会』で政権の運営がままならないからだ」

議院内閣制の内容もわからない相手に、英語で説明するのは大変でした。分からない単語は電子辞書で調べながらなんとか理解してもらいました(本当に理解してもらえたのかな?)
議院内閣制では、行政権の長は直接国民からは選ばれず、議会の信任を必要とします。またイギリスも議院内閣制をとっていますが、議会の上院は非民選で下院が圧倒的に優越しているため『ねじれ現象』など起こらないのですね。
英語で⁉
梅雨なのに梅雨らしくない天気に多少もやもやしている島崎です。
これも,地球温暖化の影響なんでしょうか?
環境と言えば,先日軽井沢でG20の環境相サミットが開催されたようです。
海洋プラスティックごみ問題について議論されたようですが…
自分が気になったのは,海洋プラごみ問題の中身よりも,
別の見出しでした。
「長野高生サミットで英語によるスピーチを」
といった感じの見出しでした。
ここで感じた違和感は,
「なぜ”英語による”が問題なんだ⁉」というものです。
本来ならば,サミットでスピーチをするに値する内容自体が,
その内容を考え付いたことが素晴らしいのであって,
英語で,というのは問題ではないはずなのです。
どこまでいっても,英語は”外国語”なんでしょうね…
外国語であっても,伝える手段と考えれば,
英語は習得できます。
でも,「話す中身・伝える中身」を身に付けるのは,英語の学習ではありません。
話す中身を持った人になって欲しいなぁ,という想いを新たにした島崎でした。
こういうときに思うこと
昨夜、新潟県で震度6強の大きな地震がありました。
このブログを書いている段階で被害の全容はわかっていませんが、被害が最小限のものであることを心から祈っています。
高校の理科は、「物理」「化学」「生物」「地学」の4科目となっています。
さらに現行の指導要領ではそれぞれの科目が、2単位の「物理基礎」「科学基礎」「生物基礎」「地学基礎」と4単位の「物理」「化学」「生物」「地学」に分かれています。

このブログを書いている段階で被害の全容はわかっていませんが、被害が最小限のものであることを心から祈っています。
高校の理科は、「物理」「化学」「生物」「地学」の4科目となっています。
さらに現行の指導要領ではそれぞれの科目が、2単位の「物理基礎」「科学基礎」「生物基礎」「地学基礎」と4単位の「物理」「化学」「生物」「地学」に分かれています。
理系の生徒は「物理」「化学」か「化学」「生物」を選択するのが普通です。「地学」を選択すると個別試験(二次試験)や私大で受験できるところが少ないから、というのが理由のようです(ちなみにセンター試験で「地学」の選択者は「化学」選択者の100分の1くらいです)。
地学は文系の生徒が「生物基礎」「地学基礎」の組み合わせで選択するくらいのもので、4単位の「地学」を履修する人はかなり少なくなっているのが現状です。

そもそも「地学」は、「地球物理」「大気・海洋」「地質・地史」「天文」などの分野が含まれており多岐にわたります。そのため「地学」の指導者自体が不足しているという話も耳にしたことがあります。
しかしながら、「地学」は地震・異常気象・火山・自然災害など私たちの生活と密接な関係にある科目でもあります。「地学」に関心を持ってくれる高校生が増えてくれればいいなと、ことあるごとに感じています。
「物理」「地学」の選択は、ある意味『黄金パターン』だと思いますがね(勝手に)。
単なる独り言になってしまった 学長でした。
『定期考査』スタート
長野高校の2・3年生は、今日から『定期考査』がスタートします(1年生は明日から)。

いつでも来て大丈夫ですよ。お昼ご飯もラウンジで食べられますからね。

ちなみに明日は長野日大のテスト対策で13:10から授業も入っています。
こっちも気合いが入ってきた 学長でした。
テスト期間中は早く終わるので、自習室は清掃も終えて、冷房も入れてすでにスタンバイOKです!!


さあ3日間頑張り抜きましょう!!
ちなみに明日は長野日大のテスト対策で13:10から授業も入っています。
こっちも気合いが入ってきた 学長でした。
次は コレ!! ・・・???
長野吉田高校 吹奏楽班の定期演奏会も終わり、

そう、『文化祭』です!! ・・・???
いやいや、その前に『定期テスト』ですよね。
附属中学は今日、長野高校は明日から、長野日大は明後日から『定期テスト』が始まります。
長野西・長野東・市立長野・清泉女学院などの高校、長野東部・北部・市立長野附属などの中学校は来週が『定期テスト』となります。
みなさん頑張ってください。
できる限りテスト前のフォローを入れられるように、私も頑張ります!!
次は 『コレ』ですね!!

長野西・長野東・市立長野・清泉女学院などの高校、長野東部・北部・市立長野附属などの中学校は来週が『定期テスト』となります。
できる限りテスト前のフォローを入れられるように、私も頑張ります!!
ベタなノリツッコミはやめようと思った学長でした。
追記)長野吉田高校は、今年は異例で「文化祭」の後に『期末テスト』が組まれています。文化祭からテストまで10日ぐらいしかありませんから、それなりの準備(もちろんテストの)はしておいてくださいね。
取扱注意『やればできる』
「やればできる」かなりの確度で正しいと思います。
しかし、この「やればできる」という言葉は、くれぐれも取り扱いに注意してください。
【悪い使い方】
「やればできる」とただ単にひたすら言い続ける
↓
「やれば」という仮定のままで、ずっと「やらない」状態がつづく。
↓
「やらない」のでいつまでたってもできるはずがない
※このタイプの子どもに「やればできるよ」と言うと「よく言われます」と答えることが多い(笑)。
【良い使い方】
「やればできるよ」
↓
様々な手を使ってでもとにかく「やらせる」
↓
結果を出させる(結果が出そうなところを選んでやらせる)
↓
「ほら言ったとおり、やればできるだろ。」

「やればできる」という言葉は言うだけでは、根拠のない自信ばかり育て、「いつの日かやりさえすればボクだって・・・」という現実逃避にさえ使われる危険性があります。
大切なのは「やればできる」という言葉と現実の成功体験を結びつけてあげることです。
そのために誤解を恐れずに言えば最初の部分で「半ば力づくでも」やらせることが必要になります。
生徒の自主性、個としての尊重が叫ばれるなか、時代に逆行しているように聞こえるかもしれませんが、止まっている歯車を回し始めるにはそれなりの『力』が必要となります(もちろん生徒に物理的な力を加えるわけではありません)。
「やらせること」、やわらかく言うなら「やってもらうこと」、そこから本当の「やればできる」は始まります。
「やる気」より「やる」のが先!! 学長でした。
365歩のマーチ
昨日ブログの管理画面を開いたら「連続投稿40日おめでとうございます」といった文言が出ていました。
私の不精な性格から、今まで40日もブログを書き続けたことがなかったのでびっくりしました(もちろん休みの日には島崎先生に書いてもらってますが)。
ただ、このあと恐怖の(笑)『夏期講習』が始まるとどこまで続けていけるのやら・・・・ 少し(いや大変)不安になります。
そんなことを考えていたとき頭に浮かんできたのが、『365歩のマーチ』です(古すぎますかね)。
ご存知水前寺清子さんの歌で、作詞は星野哲郎さんです。
「一日一歩 三日で三歩 三歩進んで二歩下がる~♪」
あらためて歌詞を読み返してみると、受験生も元気づけられるような気がしました。
「あなたのつけた 足あとにゃ きれいな花が咲くでしょう~♪」
みんなの一日一日の努力が、合格という花を咲かせてくれることを切に願っています。
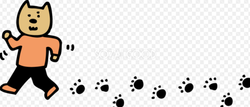
私の不精な性格から、今まで40日もブログを書き続けたことがなかったのでびっくりしました(もちろん休みの日には島崎先生に書いてもらってますが)。
ただ、このあと恐怖の(笑)『夏期講習』が始まるとどこまで続けていけるのやら・・・・ 少し(いや大変)不安になります。
ご存知水前寺清子さんの歌で、作詞は星野哲郎さんです。
あらためて歌詞を読み返してみると、受験生も元気づけられるような気がしました。
「あなたのつけた 足あとにゃ きれいな花が咲くでしょう~♪」
みんなの一日一日の努力が、合格という花を咲かせてくれることを切に願っています。
「腕を振って 足を上げて ワンツーワンツー 休まないで 歩け~♪」
さぁ 夏を迎えますが、元気を出していきましょう!!
「千里の道も 一歩から はじまることを 信じよう~♪」
以上、学長でした。
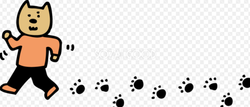
野村克也氏の金言
中学3年生は、前回の復習テストが終わり、まもなく次の復習テストが待ち受けています。
前回成績を伸ばした生徒たちは、「次も頑張ります」「この調子で行けば大丈夫ですよね」などと私に言ってきます。
「あぁ、この調子で次も頑張ってね」と、私は答えます。
言葉では「頑張ります」と言うものの、その態度には少し緊張感が足りないように感じるのです。
申し訳ありませんが率直に言って、「上がった分の半分ぐらいは次は下がるな」と感じるのです。

さすが名将です。私自身も身につまされるます。
生徒たちにも、成績が上がったときこそ「自分の何が良かったのか」考えられるように指導していきたいと思っています。
反省も込めて、学長でした。
前回成績を伸ばした生徒たちは、「次も頑張ります」「この調子で行けば大丈夫ですよね」などと私に言ってきます。
「あぁ、この調子で次も頑張ってね」と、私は答えます。
しかし、実際にはある種の違和感を感じています。
申し訳ありませんが率直に言って、「上がった分の半分ぐらいは次は下がるな」と感じるのです。
以前、野村克也氏のこのような言葉を聞いたことがあります(ずいぶん前でしたので不正確でしたら申し訳ありません)。
『二流の選手は、スランプに陥ったときに「自分のどこが悪いのか」を考える。一流の選手は調子のいいときに「自分のどこが良いのかを考える。』

生徒たちにも、成績が上がったときこそ「自分の何が良かったのか」考えられるように指導していきたいと思っています。
反省も込めて、学長でした。
何のため⁉
島﨑です。
突然ですが,模試は何のために受けますか?
先日,高校3年生の生徒さんと模試の話になりました。
模試の試験結果の一覧が題材でした。
どうやら,志望大学に対する合否判定が気になるようです。
それも至極当然のことと思いますが…
それよりも気にして欲しいのは,全国平均との差の部分にあります。
現段階での結果ですから,差があるのは当然なのですが,
その差がどれくらいあるのか,の方が問題だからです。
ところで,平均との差以上に重要なものがあると言ったら何だと思いますか?
それは解説書の存在です。
解答・解説として配布される冊子の重要性を知って欲しいと思います。
解答・解説は,「現段階でわかっているべきこと,知っているべきこと」が
端的にまとめられた絶好の参考書なのです。
自分が高校生だった頃(はるか遠い昔になってしまいましたが…),
自分は模試を受ける理由を「解説書を手に入れること」に置いていました。
ですから,模試の結果も合否判定も気にはなりませんでした。
模試の後,どれだけ解説書を読み込んだか,が
本番での結果につながると考えます。
受験生の皆さん。
模試とは「解説書を買うこと」と考えると,結果に左右されずに,
ブレずに本番に向かうことへの王道を進んでいけるかもしれませんよ。
柄にもなくまじめにコメントしてみた島崎でした。
人を見て法を説く
生徒が、わからない生徒に勉強を教える。
よく聞く話です。
互いに助け合う、微笑ましい光景ですが、実は気をつけなければならないことがあります。
このような仕事をしていてつくづく感じるのですが、生徒が生徒に教える場合、「教える側」には大きなメリットがありますが、「教わる側」にはデメリットが生じることも少なくありません。
「教える側」は、人に教えることによって自分の理解度を深めることができます。実際、教わった生徒がその内容を先生に説明するという『ユダヤ式学習法』というものもあります。私も、中学生に理科などを説明したとき、誰でもいいからつかまえて今の内容を説明するようにと指示することがあります。


よく聞く話です。
互いに助け合う、微笑ましい光景ですが、実は気をつけなければならないことがあります。
このような仕事をしていてつくづく感じるのですが、生徒が生徒に教える場合、「教える側」には大きなメリットがありますが、「教わる側」にはデメリットが生じることも少なくありません。
「教える側」は、人に教えることによって自分の理解度を深めることができます。実際、教わった生徒がその内容を先生に説明するという『ユダヤ式学習法』というものもあります。私も、中学生に理科などを説明したとき、誰でもいいからつかまえて今の内容を説明するようにと指示することがあります。
一方「教わる側」のデメリットとは何でしょうか?
一言で言うと「教える側の『教え方の選択枝』が少ない」ということです。
単純な例で説明します。次の計算をどのように教えるでしょうか?

この場合、よくある教え方は次のふたとおりです。

①はルートの中の数を大きくしてさらにそれを素因数分解していくという、かなり煩雑な計算となります。
それに対して②は計算がシンプルな分、計算ミスも少なく時間も短縮できます。
②のほうが①より優れていることはご理解いただけると思います。
しかし、生徒が理解しやすいと感じるのは①の方なのです。
生徒がわからない生徒に教えるときも、①の計算方法のほうが多いようです。
私も、数学がどうしても苦手で「総合テストでなんとか計算問題だけでも得点したい」という場合には、①の計算方法を教える場合もあります。
しかし、先々の数学の発展のことを考えれば、最初はとっつきにくくてもできる限り②の計算方法をマスターしてもらうように努力しています。
大切なのは「教える側」が教え方の選択肢を複数持っていて、その生徒に応じた必要十分な解法を提示できるかということです(高校生になるともっと極端で「理系」の生徒と「文系」の生徒では教え方もかなり変えていきます)。
「学生アルバイト」の講師についても同じことが言えます。多くのアルバイト講師は「自分なりの解法」しかもっていません。
『人を見て法を説く』ことこそが「教える側」にとってもっとも大切なことなのです。
以上、学長でした。