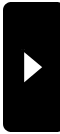目が離れる
「計算ミス」にはいくつか典型的な原因があります。
そのひとつが『目が離れる』です。

数学の問題を解いているとき、解き方の手順が見えた瞬間に「これでいける」と感じます。
これは「反射」のような感情で、押さえ込むことは難しいと思います。
ただ、「これでいける」と感じた次の瞬間、それまで懸命に解法を模索していた反動で、一瞬ホッとして集中が切れてしまうことがあります。
「あとは計算処理だけだ」と思ったときに、次の問題のこととか、残り時間のこととか、ほかのことが一瞬脳裏をよぎるのです。
私はこれを『目が離れる』と言っています。
「できた」と思った次の瞬間が、計算ミスを起こす危険性が非常に高くなるんですね。
まずは『この傾向』をしっかり意識して、「できた」と思ったらひと呼吸入れて仕切り直すくらいの気持ちで問題に臨めば、計算ミスを少なくすることができると思いますよ。
是非 試してみてください。
これって数学以外にも通じるところが多いよな と思った学長でした。
PS.投票は済ませてきました。これから授業です。
議院の権能
明日は参議院議員選挙なので、政経の問題を1題。
④ 参議院議員を懲罰するには、衆議院の議決も必要である。

考え方の基本は、「衆議院」と「参議院」が一緒になって初めて『国会』になるというこちです。
衆議院だけ、参議院だけでは、国会にはなりません。
ですから、国会の会期中に衆議院が解散したときは、参議院は同時に閉会になります。
よって②は正しい記述です。
衆議院と参議院は原則対等で、両院で可決したときのみ国会の議決となります。
どちらか一方が否決すれば、国会の議決とはなりません。
なお、重要事項について両院の議決が食い違い何も決められないとなると、国政が停滞してしまいます。
そのため、「法案の議決」「予算の議決」「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」など一定の重要事項について両院の議決が食い違ったときに「衆議院」の議決を「国会の議決」とする『衆議院の優越』が認められています。
憲法改正の発議も両院対等です。参議院が賛成しない以上、国家は発議できません。
よって、③は誤った記述となります。
衆議院と参議院が一緒になって初めて国会となるのですが、衆議院・参議院の各議員がそれぞれ単独で行うことができることもあります。
それが『議院の権能』とよばれるものです。
「国政調査権」「議院の規則制定権」「所属議院の懲罰権」などがこれにあたります。
よって①・④は「議院の権能」であり参議院が単独で行うことができるので、誤った記述となります。
以上から、②が正解となります。
ちなみに、私は明日出勤前に投票してくる予定です。
次の①〜③の中から正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。
① 参議院が国政調査権を行使するには、衆議院の同意が必要である。
② 国会の会期中に衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会となる。
③ 憲法改正の発議で、参議院が否決した場合には、衆議院で総議員の3分の2以上の賛成があれば国会の発議となる。④ 参議院議員を懲罰するには、衆議院の議決も必要である。

衆議院だけ、参議院だけでは、国会にはなりません。
ですから、国会の会期中に衆議院が解散したときは、参議院は同時に閉会になります。
よって②は正しい記述です。
衆議院と参議院は原則対等で、両院で可決したときのみ国会の議決となります。
どちらか一方が否決すれば、国会の議決とはなりません。
なお、重要事項について両院の議決が食い違い何も決められないとなると、国政が停滞してしまいます。
そのため、「法案の議決」「予算の議決」「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」など一定の重要事項について両院の議決が食い違ったときに「衆議院」の議決を「国会の議決」とする『衆議院の優越』が認められています。
憲法改正の発議も両院対等です。参議院が賛成しない以上、国家は発議できません。
よって、③は誤った記述となります。
衆議院と参議院が一緒になって初めて国会となるのですが、衆議院・参議院の各議員がそれぞれ単独で行うことができることもあります。
それが『議院の権能』とよばれるものです。
「国政調査権」「議院の規則制定権」「所属議院の懲罰権」などがこれにあたります。
よって①・④は「議院の権能」であり参議院が単独で行うことができるので、誤った記述となります。
以上から、②が正解となります。
両院が共働してできる「国会の権能」と各議院が単独でできる「議院の権能」はしっかり分けて整理しておいてください。
政経・現社で受験する高校生はもちろんのこと、公民でも出題されることもありますので、できれば中学生にも知っておいて欲しいことですね。
ちなみに、私は明日出勤前に投票してくる予定です。
以上、学長でした。
ポスター
今日は簡潔に行きます。

ポスターです。
もちろん印刷は、印刷会社に頼みましたが(笑)
場所は『桐原駅』です。
場所柄、通学の高校生向きに作っってあります。
とりあえず掲示期間は3週間にしてあります。
皆様のお目にとまれば光栄です。
作りました & 貼りました。

ポスターです。
もちろん印刷は、印刷会社に頼みましたが(笑)
場所は『桐原駅』です。
場所柄、通学の高校生向きに作っってあります。
とりあえず掲示期間は3週間にしてあります。
皆様のお目にとまれば光栄です。
以上、あっさりと学長でした。
毎日アップデート
夏期講習会の準備に追われ,若干焦り気味の島﨑です.

というのも,テキストは自作ですし,
毎年リニューアルを繰り返しているからなのです.
絶対に必要で,必ず押さえておかなければならない点には
それほど変化があるわけではないのですが,
それでも毎年講義するたびに
「ここはこう話しておくべきだった」,
「この話よりもあの話を先にしておくべきだった」などなど,
反省材料の方が多いくらいです.
長年講師と言う仕事をしていますが,
未だ完成形は見えてこず…
いつの日か理想の講師像というものを描いてみたい.
そんな想いにかられながら,
いそいそとパソコンに向かう島崎でした.
晴れ間
今日は、梅雨の晴れ間といった感じで、太陽が顔を出してくれています。

今から10年くらい前になりますが『脳からストレスを消す技術』(有田秀穂著)という本を読みました。
サブタイトルが「セロトニンと涙が人生を変える」です。
現代社会においてストレスを受けることは避けられないことであり、「どんなに頑張っても、人はストレスに打ち勝つことはできない」と書かれていました。
ですから、ストレスとうまく付き合うことが大切で、そのカギを握るものとして『セロトニン』という物質が紹介されています。
セロトニンとは神経伝達物質の一つで,ドーパミンやノルアドレナリンなどの感情的な情報をコントロールし、心のバランスを整えてくれる働きがあり、別名「幸福ホルモン」と呼ばれているそうです。
そして、セロトニンを分泌させるセロトニン神経を興奮させることができるのが『太陽の光』であると書かれていました。

サブタイトルが「セロトニンと涙が人生を変える」です。
現代社会においてストレスを受けることは避けられないことであり、「どんなに頑張っても、人はストレスに打ち勝つことはできない」と書かれていました。
ですから、ストレスとうまく付き合うことが大切で、そのカギを握るものとして『セロトニン』という物質が紹介されています。
セロトニンとは神経伝達物質の一つで,ドーパミンやノルアドレナリンなどの感情的な情報をコントロールし、心のバランスを整えてくれる働きがあり、別名「幸福ホルモン」と呼ばれているそうです。
そして、セロトニンを分泌させるセロトニン神経を興奮させることができるのが『太陽の光』であると書かれていました。
一般に日光を15分以上浴びるとセロトニンが分泌させるようです。
梅雨時は、日差しが少なく気持ちまでどんよりするのはそのせいもあるのかもしれませんね。
私は、スクーターで通勤しているので通勤の途中と、上の写真を撮るために屋上で『太陽の光』を浴びました。
せっかくの梅雨の晴れ間です。
みなさんも『太陽の光』を是非ご堪能ください。
梅雨が明ければ『夏』、学長でした。
のぼり
昔、今より若かったとき、
(When I was younger, so much younger than today~♫)
私はこう教わりました。
塾の『のぼり』は、お店の『のれん』と同じだ。
だから、教室を開けるときに『のぼり』を出して、教室を閉めるときに『のぼり』をしまう。
『のぼり』 が出ているということは、教室が開いているという目印で、『のぼり』を見て、生徒やいろいろな人が教室を訪れる。
『のぼり』が出しっぱなしになっているのは仕事がルーズな証拠だから、そんなところに大切な子どもを預けようとは思わない。
最近はそうでもないのでしょうか。
たしかに、朝早く出勤するときなど、車の販売店さんとか『のぼり』を出されているところを目にすることもあります。
しかし、『のぼり』がずっと出ているところがけっこう多いようにも思います。

平日は13:00開校ですが、12:00前には教室に来て、掃除の前に電気をつけて『のぼり』を出します。
たまたま早く学校が終わった高校生が12時過ぎ頃に顔を出して、
「先生、もう入っていいですか?」
「あぁ いいよ。でも、掃除するからその間ラウンジ(食事や休憩用の部屋があります)で待っといてくれる?」
「わかりました」
生徒は、ラウンジで食事をしたり、勉強したりして待ってくれます。
「掃除、終わったから自習室いいよ」
「ありがとうございます」
といったこともよくあります。
『のぼり』を出しておくことによって、24時間宣伝できる。
そういう考えもあるのでしょう。
でも、うちは『のぼり』を目印にみんなが来てくれる、そんな塾でありたいと思っています。
この話を書こうと思ったときから「古いやつだとお思いでしょうが・・・」という鶴田浩二のセリフ(さすがにこれは古すぎるか・笑)が頭の中をリフレインしている 学長でした(長っ)。
ちなみに、写真の『のぼり』も自分たちでデザインしたものです。
受験感覚のアップデート
昨年(平成31年度)の長野県公立高校入試(後期選抜試験)で、もっとも平均点が低かった教科は何でしょうか?
その通り! 『理科』です。
国語70.3点 社会58.2点 数学53.6点 理科46.1点 英語53.9点
一昨年(平成30年度)に続き2年連続となりました。

その通り! 『理科』です。
一昨年(平成30年度)に続き2年連続となりました。
現在の学習指導要領の下で行われた入試(平成24年度以降)8回分の平均を見ると次のようになります。
国語62.0点 社会55.0点 数学46.7点 理科47.0点 英語53.8点
数学の平成24年度の平均点が30.1点という驚異的な数字であったことを考えると、実質的に一番平均点が低いのはやはり『理科』ということになります。

ひと昔前であれば、「理科・社会は勉強さえすればどうにかなる」というふうに思われていました。
しかし現在、多くの受験生をもっとも悩ませている教科は『理科』なのです。
『脱ゆとり教育』を掲げて、現在の学習指導要領に改訂された際、学習内容がもっとも増えたのが「理科」でした。
一方、当時すでに学校の完全週5日制は導入されており授業時間は学習内容の増加分だけ増やすことができませんでした。
果たして、そのしわ寄せが生徒に来るであろうことは当時から十分予想できていました。
「『理科』が受験のカギを握っている」と言っても過言ではありません。
クレドアカデミーが「夏期講習」で理科を【90分×9コマ】も入れている理由もそこにあるのです。
この夏、頑張って『理科』を(も?)克服してください。
以上、学長でした。
思い浮かばない(;´д`)
今日のブログのネタが思い浮かびません・・・
あせる(~ω~;)))
待てよ。
この感覚、
どこかで・・・
そういえば、遠い昔数学の問題を前にして何も思い浮かばなかったときの感覚に似ています。
今でこそ、そういう時にどうすればよいかという引き出しがありますが、高校生の頃は焦りまくっていましたね(笑)
ということで、数学の問題に対して何も思い浮かばないときどうすればよいか?
いろいろ手はありますが、その中でやっていそうで意外とやっていないものをひとつ。
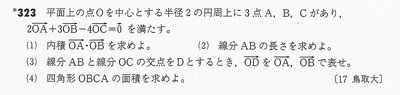
設問が(1),(2)、・・・と小問に分かれている問題で詰まったとき、前後の設問をチェックしてください。
(2)で詰まったら、(1)と(3)の『流れ』を考えるようにしてください。
極端にいえば(1)で詰まったときでも、(2)を見れば打開策が見つかることがあります。
「(2)でcosθの値を求めさせているということは, (1)で内積を求めるのに定義は使わないな」 といった具合です。
苦しまぎれのネタですが、使えますので使ってください。
白紙が怖いのはテストと同じ と思う学長でした。
― Tomorrow is another day.
『予行演習』の・ようなもの
今日から3連休です。世の中では・・・(´ω`)
ですから、今週は3日連続10:00~22:00の勤務となります。
「えっ、それってブラックじゃないの?」
大丈夫です。「私これでも経営者なので」(大門美知子風)
もともと、自分が思った通りに、生徒にやってあげられるよう自分で塾を始めたのですから。
ただ、この仕事、体力勝負であることには違いありません。

8:00前には来て冷房を入れるなど準備をしなければなりません。
タイトルの「の・ようなもの」に反応した人はけっこうな映画好きだと思う 学長でした。
クレドアカデミーは
土・日・祝日は10:00~22:00の開校です。
ですから、今週は3日連続10:00~22:00の勤務となります。
大丈夫です。「私これでも経営者なので」(大門美知子風)
もともと、自分が思った通りに、生徒にやってあげられるよう自分で塾を始めたのですから。
夏期講習会ともなると、8:30~22:00の開校になります。

朝から掃除などできませんから、前日終わったあとに掃除して帰ります。
この3日間は、夏期講習に向けて体を慣らすための「予行演習」の・ようなものですね(笑)
私もそうですが、人間はそんなに強くはないと思います。
誘惑があればそちらにフラフラと行ってしまいがちです。
家に誘惑が多いのならば、自習室に来て勉強してください。
そのために開けて待ってますからね!!
卒業までの半年で〜♫
卒業までの半年で
答えを出せと言うけれど〜♫
森田公一とトップギャランの昭和のフォークソングです。作詞は阿久悠さんですね。
昭和51年のヒット曲ですが、今の時代に照らすと大学卒業の半年前にけっこう呑気な話ですよね。
さて、7月は高校も中学も学校の三者面談が行われます。

答えを出せと言うけれど〜♫
森田公一とトップギャランの昭和のフォークソングです。作詞は阿久悠さんですね。
昭和51年のヒット曲ですが、今の時代に照らすと大学卒業の半年前にけっこう呑気な話ですよね。
高校によっては、高校1年生の面談で「志望大学」や「志望学部学科」を訊かれることがあります。
場合によっては「少なくとも学部学科についてはこの段階で決めておくべきだ」と言われることもあるようです。
確かに、進学校といわれる高校は、2年になるときに理系と文系に別れます。
そのため、早い段階で少なくとも理系に進むのか文系に進むのかを決めておいてもらわないと困る、という学校の立場もわかります。

しかし、高校1年生といえば、この春高校受験を乗り越えて、ようやく高校生になったばかりです。
大学にどういう学部学科があるのかさえ、わかっていない生徒が多いと思います。
ましてや、どの学部学科に進学し、将来どのような道を進みたいのか、決まってる生徒の方が少ないのではないでしょうか。
例えば、1学期のテストで理系科目が良くなかったとしても、そのことだけで理系学部への進学をあきらめるのは拙速です。
これまでみてきた生徒の中にも、入塾した段階で数学が学年で最下位に近かった生徒さんが、現役で国公立の理学部に合格したこともあります。
入学してからのたった3ヶ月で、一生にかかわる答えを出すのは正直難しいと思います。
自分の人生です。学校のスケジュールにうまく合わせながら、じっくりと自分の将来について考えてください。
自分が納得するまで、しっかりと考えてみることをおすすめします。
タイトルの曲は今風に言えば「アオハル時代」かな と思う学長でした。